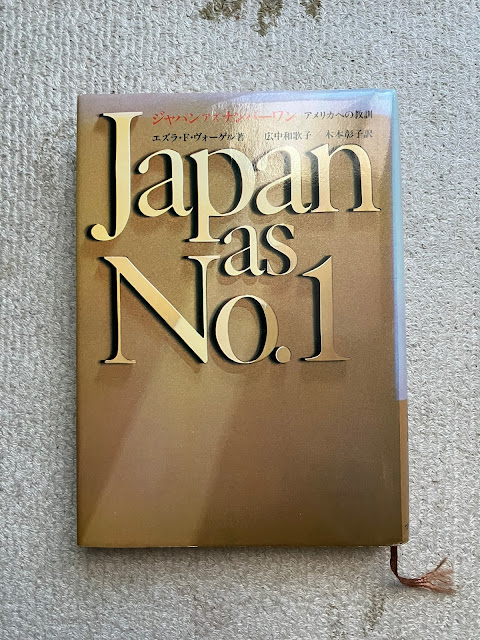メディアが果たすべき役割とは?~〝騒ぐ〟ことで流れを変える!?

「2024年問題」というワードが昨年からメディアを賑わせています。(今はかなり下火かも) この問題は、物流業界にも残業時間の規制が適用されることで、「ドライバー」という仕事が稼げない職業になり、担い手が減ったり、長距離で物を運ぶ際には運転手を交代させる必要が生じたりと、これまでとは違い、物が当たり前に届かなくなってしまう危機のことです。 先日、とある運送会社の経営者と話す機会があり、24年度に入ってからの実状を聞いてみました。 恐らく、 「人が足らなくて困っているんだよ…」 と言われるかと思いきや、決してそんなことはなく、返ってきた答えは 「むしろチャンスが来たと思っている」 との回答でした。 その理由を聞くと、 「これまでは値上げ要求なんてほとんど無理だったけど、24年問題がメディアでクローズアップされたおかげで要求に応じてくれる空気になった。取引先もこのままではまずいと思ったんでしょう」 なるほど! 私はこの話を聞いた時、 「これこそがメディアの役割ではないか!」 と感じました。 最近は何かと「マスゴミ」など、たたかれがちなメディアですが(特に大手)、 24年問題について〝騒ぐ〟ことで、何とかしなければ!という空気を作り、誰かを助けているではないですか! やはり誰しも社会にとって大きな問題があったとしても、それが身近になければ真剣に考えません。 そうした、問題と興味がない大多数の人々を結び付けるのがメディアの力です。 このような「自分たちの役割」を再認識することができれば、メディアももっと成長していくのではないかと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 人気ブログランキングに参加しています。ぜひクリックをお願いいたします。 社会・経済ランキング にほんブログ村 【X】 https://twitter.com/eskun8911nok