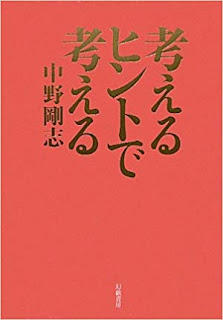インフラのないところに企業は来ない~企業の経営者になった気分で考えてみよう!~

インフラが整っていない地域に、 日々激しい競争にさらされている一般企業が来るはずがありません。 それが数字として現れているようです。 「企業誘致 遠い政府目標」 https://dbs.g-search.or.jp/aps/QCGT/main.jsp?ssid=20190326231442984gsh-ap03 …。 当たり前ですね。 自分が経営者だとしてみましょう。 生産したモノやサービスを誰かに消費してもらわなければ、 所得及び利益は生まれません。 であれば、消費者により近い場所に会社を置きたいと考えるはずです。 近い場所でなくても、 消費者がより多くいる場所に、より便利に到着できる場所を選ぶ はずです。 考えてみれば、当たり前ですね。 政府は声高に 「地方創生!」 を叫びますが、 本当にそれを実現したければ、 交通などのインフラに予算を十分に振り向け、 その整備を進めるのが筋です。 でも、 緊縮財政のせいで全くインフラ整備をしない 。 政府自身が地方創生の足を引っ張っていることがよくわかります。 やはり、緊縮財政を打破しなければ、何も始まりませんね。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 人気ブログランキングに参加しています。ぜひクリックをお願いいたします。 社会・経済ランキング にほんブログ村 【ツイッター】 https://twitter.com/eskun8911nok